市民クラブ会派行政調査報告 2025(令和7)年7月7日から9日まで
2025(令和7)年7月7日から9日にかけて、福島県伊達市、宮城県多賀城市及び石巻市を視察しました。
健幸都市づくりへの取組について【福島県伊達市】
取り組んだ経緯(背景・目的)

「健幸都市」(スマートウエルネスシテイ)とは、健幸(ウエルネス)をまちづくりの中核に位置付け、市民一人一人が健康かつ生きがいを持ち、安全・安心で豊かな生活を営むことのできるまちのこと。
伊達市は全国推計よりも早いスピードで少子高齢化が進行しており、「社会を支える若者が減少し社会参加も進まないことで、高齢者を支え切れなくなる」ことに対し、逆転の発想で、「元気な高齢者が社会を支えることを目指して、元気な高齢者を増やす」施策にシフトした。変化する社会状況に対応するためには、幅広く一体的に健幸都市づくりを進めることが必要であることから、市が実施するあらゆる施策・事業において健幸都市を推進するという視点のもと、総合政策として全庁的な取組を進めることとした。
- 2011(平成23)年11月 健幸都市宣言
- 2012(平成24)年3月 伊達市健幸都市基本構想を策定
- 2014(平成26)年5月 伊達市健幸都市基本計画を策定
- 2023(令和5)年3月 第2次健幸都市基本計画を策定し、庁内連携のもと、推進している。
取組の内容と現在の状況
第2次健幸都市基本構想・基本計画 (2023(令和5)年度から2032(令和14)年度までの10年間)
将来像「豊かな自然の中でみんなが歩いて健幸になれるまち・伊達市」の実現に向け、「歩くこと」を基軸としたまちづくりを推進している。「歩く」は、イコール「Walk」ではなく、年齢、性別、障がいの有無等に関係なく「誰もが安心して外に出ること」。
基本方針1【健康づくり】 ーいつまでも元気に歩けるからだづくりー
- 健康づくり支援の充実:スポーツを通じた健康増進、次世代の健康をつくる支援
- 健康を守る予防事業の推進:健(検)診事業の推進、健康データの活用
基本方針2【暮らしづくり】 ー自然と歩きたくなるまちづくりー
- 歩く機会の創出:地域資源を活かした事業、商店街等と連携したイベントの拡充
- 人や地域の交流促進:支え合い助け合う地域づくり、安全・安心な地域づくり
基本方針3【ひとづくり】 ー歩いて健幸になる意識づくりー
- 健幸意識の醸成:学校、職場、地域での意識醸成
- 健幸なまちづくりのための人材育成:担い手や地域コミュニティの土台づくり
主な取組事例
「だてな健幸ポイント事業」
健康づくり無関心層を含めて、多数の住民の行動変容を促す制度として創出。福島県の「ふくしま健民パスポート」と連携をして展開
※2025(令和7)年3月末現在:参加者3,747人(アプリ利用:3,262人(87.1%)
- 「健幸クラブFine」(通所型運動支援事業)
40歳以上の市民を対象に介護予防・フレイル予防に取り組む健康運動教室を市内5カ所で実施。主にマシンを使用し、健康運動指導士等による個別指導支援
※2025(令和7)年3月末現在会員数 65歳以上 1,235人、64~40歳 430人
「働き盛り世代の健康づくり」
働き盛り世代・健康無関心層への働き掛けとして、事業所と連携して実施しており、従業員の健康づくり(運動不足の解消、メタボや生活習慣病の予防)に活用
- 事業所向けだてな健幸ポイント普及事業
- 健康機器貸出事業
エアロバイク、体重体組成計、血圧計を無料で1~2台貸出(期間は6カ月) - 出張版健幸クラブFine
運動指導員を派遣し、健康運動教室「出張版健幸クラブFine」を実施
「元気づくり会」
身近な場所で健康づくりに取り組む人を増やす仕組みとして、主に町内会単位で、集会所を会場として市民主体の健康運動活動の実施
- 集会所コース
元気づくり会を体験する教室型で、6カ月間コーディネーターと体験実施 - 元気リーダーコース
経験者の希望者が自主運営型で元気づくり会を継続
※実施会場数:現在153カ所の身近な会場で活動
成果・課題・今後の取組
- 「だてな健幸ポイント事業」の参加者が年々増加。また、健幸都市拠点として整備した「伊達市ウェルネスサロン白根」の使用率も伸びてきている。
- 1日1時間以上運動する人の割合が増え、メタボ該当者や予備群の割合は減少傾向にあり、目的の一つでもある要介護・要支援を受けている高齢者の割合も年々減少傾向にある。
- 健幸都市関連事業は、全市展開としているため、「全体的な効果」として肥満の割合、医療費や介護費といった医療に関する指標の移り変わりに注視していく。
- 計画の早い段階から事業実施効果が見えるようにしていくことは重要であるため、「全体的な効果」と併せて「部分的な(成功的な)成果値」の把握にも努めている。
- 今後の取組として、健幸になるためには、”健康づくり”だけでなく、”暮らしづくり”、“ひとづくり”が大切である。観光振興、景観整備、道路警備、就労支援、子育て支援、教育、生涯学習、地域づくり、医療、公共交通、デジタル化推進など、様々な取組が必要であるため、庁内関係課にも健幸マインドを持ってもらう。
所感・大府市への反映
- 本市と同じ、働く世代への働き掛けに苦労していた中で、働く世代に着目して、健康器具を貸し出すアイデアは非常によいと感じた。本市でも働く世代にアプローチする施策が必要であると思う。
- 健康づくりの意識を高め、約400人の「健幸づくり推進員」が約380の町内会から選出されていることには驚いた。任期を1年として、まずは推進員として自身が健康づくりに関心を持ってもらうことを優先しており、より多くの人に関与してもらう姿勢が大切であると感じた。
- 健康づくりを、各個人ではなく地域で取り組む仕掛けとして自宅近くの集会所で実施できる環境としており、交通機関に頼ることなくできるやり方は参考にしたい。
- いつまでも元気で過ごせるように、本市でも若い世代や働き盛り世代への取組を強化していかなければならないと考える。
減災都市宣言・防災と減災の取組について【宮城県多賀城市】
東日本大震災による被害の状況

- 2011(平成23)年3月11日14時46分頃
- 最大震度5強、津波高 仙台港:約7メートル、市内:約2~4.6メートル
- 浸水面積:約6.62平方キロメートル(市域の約33%)→流入物推計:自動車約8,500台が市街地流入
- がれき推計量:35.5万トン
壊れた家の数:11,000棟以上 - 市内死者数:188人(市民97人、市民以外91人)、避難者数:最大約12,000人
- 応急仮設住宅 借上仮設住宅市内居住戸数:1,076戸、仮設住宅入居戸数:355戸
取り組んだ経緯(背景・目的)
震災復興計画
現地再建を基本に、10年間で震災からの復旧・復興を目指すための計画
- 復旧期3年ー現状ー
市民・企業の再建意思、市街地における被災、狭小な地域 - 再生期4年ー重点課題ー
市民生活再建と産業振興、災害に応じた安心安全の確保、まちの魅力向上 - 発展期3年ー復興に向けた施策ー
居住と雇用確保、産業振興と立地支援強化、歴史・景観・文化の活用、減災対策充実強化、防災意識の向上、震災経験の伝承
減災都市を目指して、「減災都市宣言」を掲げて推進
多賀城市では2013(平成25)年10月31日に減災都市戦略を策定した。2013(平成25)年11月28日、多賀城市減災都市戦略に掲げる将来像を目指して、市民、企業、大学などが一体となって減災に取り組んでいくこととして、減災都市宣言を行った。
悠久の歴史と伝統に培われてきたわたしたちのまち多賀城は、古くは貞観地震、近年では8.5豪雨と9.22豪雨など、多くの自然災害に見舞われてきました。
とりわけ東日本大震災がもたらした壊滅的な被害を前にして、わたしたちは自然に対する無力さを実感し、畏敬の念を新たにしました。
大雨、台風、土砂災害、地震、津波など、わたしたちの想定を超えるような大災害が、いつまた起こらないとも限りません。
わたしたちは、いつかまた来る災害に備えて、自然の猛威と脅威を乗り越えてきた先人とわたしたち自身の経験・教訓を風化させることなく、未来に継承していかなければなりません。
一人ひとりがまちづくりの主体者であることを意識し、自助、共助、公助の役割分担と相互連携のもと、日々、歴史に学び、災害による被害を最小限に抑える「減災」の取組を進めていきます。
そして、わたしたちは、人命を第一に考え、災害に備え、災害による被害を極力減じ、迅速に復旧復興するまちを目指して、ここに『減災都市 多賀城』を宣言します。
取組の内容と現在の状況
多賀城市減災都市戦略 災害に強いまち『減災都市 多賀城』
- 災害に強い都市形成
・戦略1 津波対策・多重防御戦略
現地再建を支える礎として、大津波による被害軽減される施設・仕組みを構築
・戦略2 地震に強いまちづくり戦略
市内建築物の耐震化
・戦略3 雨水浸水被害軽減戦略
大雨による浸水被害の軽減
・戦略4 災害体制確率戦略
災害発生時の救助、救援、避難、復旧などの実施体制が確立 - 自助・共助の減災力向上
・戦略5 自助力強化戦略
自助力を強化するための環境整備
・戦略6 地域防災力・減災力向上戦略
地域の防災・減災力を高め、共助の体制を整備 - 被災経験の伝承
・戦略7 震災経験伝承戦略
被災経験、記録等を伝承し、次の災害に備える - 減災技術の集積・創出
・戦略8 減災リサーチパーク構想戦略
災害による被害を軽減させる様々な技術・製品が集積・創出
成果
【ハード面での整備】
- 避難道路の整備
市内の交通量が多く、車両での避難のため、避難方向への道路整備を進めた。津波避難道路上には、大型LEDビジョンを設置し、防災アプリと連動した避難情報をリアルタイムに配信できるよう設計され、平時は市政情報などを配信している。 - 災害公営住宅の建設
市内4カ所に計532戸の住宅を建設。屋上に備蓄品倉庫を備え、有事には、避難所としても機能するものとしている。 - 復興拠点整備事業
震災時の教訓として、備蓄品やその後の支援物資を受け入れ、仕分けするスペースがなかったため、大規模な倉庫機能を持った拠点整備を進めた。平時は屋内スポーツ施設として使用し、有事の際に物資の集積場所として考えられている。同時に、災害直後の物資の運搬の課題に対し、分散備蓄も進んだ。
【ソフト面の整備】
- 防災手帳の活用
- ハザードマップの活用
最悪条件下を想定したマップを策定し、市内全世帯へ配布 - 総合防災訓練の実施(毎年11月に市内全域で実施)
【新しいまちづくりと新たな取組】
- まちのにぎわい創出
震災復興のシンボルとして、市立図書館を駅周辺の中心市街地整備事業の中核施設として整備。多賀城南門の復元と周辺歴史遺産のガイダンス施設を建設 - 災害情報伝達手段(防災情報アプリ)
避難行動を必要とする災害に特化したプッシュ型通信。気象・地震・津波に関する情報配信をサイレンや自動音声で通知。風水害時の警戒レベルの表示やハザードマップなど災害に特化し、特に高齢者にはお守り代わりとしてインストールを啓発 - 災害備蓄品管理のDX化
仙台市のシステムに相乗りし、備蓄品の管理システムを導入。システムの維持管理費は年110万円程度。備蓄品の入れ替えも外部委託し、その費用も併せて年間200万円程度の維持費で運用。QRコードを活用し、備蓄品の保管場所、消費期限、品目などシステムをPCだけでなく、モバイルでも操作可能であり、災害時には備蓄品の消費状況もリアルタイムで把握が可能 - 防災行政無線、IP無線機の導入 (職員間の災害時の情報共有)
市内55カ所に設置した無線放送機器を、トランペット型から音声が全方位で聞き取りやすいスリムスピーカーに更新。IP無線機は、従来のトランシーバー型から更新し、携帯電話のLTE回線を使用することで映像や現場写真を地図上に表示することも可能になり、状況把握が早くなった。無線機にTeamsの機能があり、映像の共有だけでなく、指示などの記録も端末に残すことができるようにした。
所感・大府市への反映
- 震災復興には、生活基盤の立て直しを何よりも迅速に行うことが重要とのことであった。
- 浸水区域や範囲を更新した際は、影響度合いを考慮して、避難者の想定も改定する必要があり、本市も実施すべきと思う。
- 災害における津波被害は、川を遡上して氾濫する可能性は充分に考えられるため、災害対策として、河川の氾濫防止に向けた整備を関係機関に働き掛ける必要がある。
- 災害用備蓄品の管理DX化は、本市では、まだ台帳等の管理は手作業で行われている。DX化することで、リアルタイムでの現状把握も可能になり、職員負担等が軽減されることから、本市でも直ちに導入すべきである。
- 多賀城市が導入した「防災情報アプリ」は、避難行動が求められるものに特化したアプリとなっており、本市も防災に特化したアプリを導入すべきと思った。
震災からの復興の取組について【宮城県石巻市】
取り組んだ経緯(背景・目的)
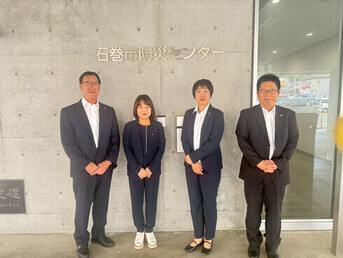
東日本大震災の概要
2011(平成23)年3月11日14時46分
石巻市(桃生地区震度6強)
- 浸水総面積73平方キロメートル(市域約13.2%、平野部約30%、中心市街地全域100%)
- 人的被害3,062人(死者数3,188人、行方不明者414人)
- 建物被害56,709棟(石巻市76.6%)うち全壊が20,044棟
- ライフライン
電力 市内全戸停電(96,277戸)
水道 市内全戸断水(60,661戸)
都市ガス 契約全戸供給停止(12,755戸)
固定通信 全地域不通

【災害対策本部での対応】
初動期
- 避難広報は防災行政無線のみ
- 救出救助は通信途絶のため要請困難
- 災害拠点病院、地元医師会との連絡不可
- 職員の安否確認不可⇒通信途絶
※災害時の通信手段の確認が課題

応急期
- 限られた資源の中での優先順位の判断が困難
- 資源の配分が不適切
- 的確な判断、指示の困難
- 職員が肉体的、精神的極限状態
⇒被災者の状況把握と限られた支援物資の運用
※応援整備が課題
【避難所】
- 最大避難者数 50,758人
- 最大避難所数 259カ所
⇒発災初期の必要品、環境変化や劣悪な衛生環境の継続による精神的強ストレスにより気力・体力・免疫力低下になり、震災関連死へと繋がった。
※避難者が定員より多く、キャパオーバーとなり、避難所環境の改善が課題
【救援物資】
- 発災1~3日目 全てにおいて不足
- 発災4日目~ 職員により物資配送を一部開始
- 1週間~2週間 自衛隊による物資管理配送
- 2週間~3月末 在宅避難者への配送拠点の設置及び配送開始
※ニーズと供給のタイムラグ、ニーズに合わない支援物資が課題
【災害広報】
- 防災行政無線 発生直後から災害情報や避難の呼び掛け
- 広報車の巡回 発生直後から避難の呼び掛け
- 情報掲示 本庁舎4階に時系列災害情報を掲示
※通信途絶のためアナログ手法により発信
【災害廃棄物の処理状況】
- 発生推計量:629万トン(通常のゴミ処理量の約108年分に相当)
- 他自治体の協力を得て、全国での広域処理により約3年で処理できた。
【市職員の被災状況】
- 2010(平成22)年 1,640人(職員の犠牲者 48人、家族の犠牲者98人)
- 住居等の被害⇒職員の被災率56.8%
※職員の心のケアが課題
【他自治体からの職員派遣状況】
- 2011(平成23)年度~2021(令和3)年度まで延べ1,750人
取組の内容と現在の状況
「石巻市震災復興基本計画」 2011(平成23)年12月22日策定(10か年)
復旧・再生のための新たな産業創出や減災のまちづくり等を推進しながら、快適で住みやすく、市民の夢や希望を実現する「新しい石巻市」の創造を目指す、復興に向けた道標とした。
基本理念
- 災害に強いまちづくり
・海岸保全施設整備(防潮堤)
・高盛土道路整備(津波多重防御)
・河川改修(堤防復旧・新設)
・海岸保全施設整備(水門・陸閘等)
⇒復旧・新設整備約200施設(うち95%に自動閉鎖システムを整備)
・防災集団移転促進等(新市街地・半島高台整備、復興公営住宅整備)
・避難所等機能整備(津波避難ビル35カ所・避難タワー4カ所等)
・災害時備蓄計画(公共施設等を合わせ68カ所以上に分散備蓄)
・防災行政無線等(音声+SNSツール、防災ラジオで発信) - 産業・経済の再生
- 絆と協働の共鳴社会づくり
「石巻防災基本条例」
基本理念
- 「自助・共助・公助」を基本とし、相互に補完し合い、協働する。
⇒自主防災組織、防災士、自主防災組織の強化機能、総合防災訓練 - 震災経験から得た知識及び教訓を後世に伝え、今後の災害に備える。
- 国内外の団体及び人々から受けた支援の絆を発展させ、我が国及び世界各国の防災への取組に貢献する。
<自主防災組織> 232組織(組織率59.9%)
大規模災害時は、救援活動の主体(自治体・警察・自衛隊など)も被災
⇒「行政機関による初動対応の限界」(組織的な活動開始までに時間が掛かる)
共助(必要性)行政が機能し救援活動開始までの補完
・自分の命は自分で守る、自分たちの地域は自分たちで守る
(役割)災害による被害予防と軽減
・避難の呼び掛け、避難誘導、救出・救助、避難所運営
<防災士>
教訓:地域防災力の必要性
※取得費用の全額を補助し、市主催の養成講座で令和4年までに417人が取得
令和元年5月 石巻市防災士協議会設立 地域の防災リーダーとして活躍
(平常時)地域防災力の底上げ (発災時)組織的な活動 (発災後)組織的な連携
今後の取組
- 新しい津波浸水想定(最大最悪)を踏まえた防災対策
- 石巻市震災遺構を今後の防災にどのように生かし、後世に繋いでいくのか検討
所感・大府市への反映
- 常に災害対策として、想定外を想定内とするために、最悪の状況で物事を判断すべきと強く感じた。
- 災害時には誰もが被災者であり、職員さんも被災者であり、発災直後の公助の課題についても考えさせられた。組織的な活動開始までに時間を要し、行政が機能し救援活動開始までの補完として「自分の命は自分で守る、自分たちの地域は自分たちで守る」共助の必要性を再認識し、地域でできることや自分たちでできること課題など話をしていく必要性を感じた。
- 減災や災害の初動活動に対し、防災士を育成確保していくことの重要性を感じた。本市でも防災士を増やす取組を個人だけでなく、民間企業にも協力を依頼して、市内全体で防災士を増やしていけるようなことを考えたい。
- 未曾有の経験は、後世に伝え風化させてはいけないと思った。本市でも東海豪雨の経験を伝え続けなければならない。


このページに関するお問い合わせ
議会事務局 議事課
電話:0562-45-6251
ファクス:0562-47-5030
議会事務局 議事課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
