公明党会派行政調査報告 2025(令和7)年7月23日から25日まで
2025(令和7)年7月23日から25日にかけて、山形県酒田市及び新庄市並びに宮城県仙台市を視察しました。
「日本一女性が働きやすいまち」について【山形県酒田市】
取組の背景、目的について

酒田市は、2017(平成29)年10月に「日本一女性が働きやすいまち」を宣言した。背景には、深刻な生産年齢人口の減少、特に若年女性の域外流出という社会課題があり、地域の持続可能性を脅かす要因として認識されていた。これを受けて、2017(平成29)年6月に「酒田市女性活躍推進懇話会」が設置され、同年10月には、官民協働で女性の就労・活躍支援に取り組む方針が打ち出された。宣言後は、「行政・企業・地域・家庭が連携・協力して『日本一女性が働きやすいまち』を実現することによる人口減少の抑制」が総合戦略での重点施策として位置付けられた。
現の取組内容について
(1) 女性の就労・起業支援 ・「サンロクIT女子プロジェクト」:市内在住の女性を対象にした在宅可能なIT講座による学習機会を提供し、スキル習得を通じた就労促進を図っている。
創業・事業承継支援員による伴走支援:創業希望の方を対象に、事業計画の策定等の相談から資金調達に対する支援から創業後のアフターフォローまで、専門家が継続的にサポートしている。
(2) 保育・子育て支援 ・病児保育、一時預かり、延長保育、休日保育といった多様な保育メニューを整備。実際の利用実績は高く、働く家庭のニーズに応えている。
病児・病後児保育の付随サービスとして、2019(平成31)年度からは「病児送迎サービス(保育所等で急に体調不良となった場合に、看護師又は保育士がタクシーで保育所等まで迎えに行き、かかりつけ医受診後に専用施設で病児保育を実施)」と「受診付き添いサービス」の提供も開始された。
|
2024(令和6)年度利用実績 |
|
|---|---|
| 病児・病後児保育の利用人数(実施1カ所) | 136人(利用延人数506人) |
| 保育所での体調不良児対応(保育を継続し、保護者の就労を支援)(実施17カ所) | 利用延人数2,102人 |
| 未就園児の一時預かり(実施19カ所) | 利用延人数1,542人 |
| 延長保育(実施23カ所) | 利用延人数14,187人 |
| 休日保育(実施1カ所) | 利用延人数44人 |
現在の課題等について
(1) 一般事業者における女性管理職登用については、市の奨励金として20万円を支援しているが、2022(令和4)年度から2024(令和6)年度の間では交付実績はない。男女の平均賃金格差の解消は道半ばであり、引き続き民間企業を含めた意識改革と制度支援が求められている。
(2) 女性に負荷がかかる構造的課題もあり、「女性活躍=女性の頑張り」とならないよう、男性の家事・育児参画促進なども課題である。
(3) 地域全体としてのジェンダー平等に対する意識変容には時間を要するため、啓発・教育活動が継続的に必要である。
今後の取組について
酒田市では、地元企業へのえるぼし支援や認定企業との連携施策が今後の女性就労促進に資すると考え、取り組まれている。「えるぼし認定」は、女性活躍推進法に基づき、企業の女性採用・継続勤務・管理職登用等の状況を評価する認定制度であり、特に女性の管理職比率や働き方改革を実行している企業に与えられる認定で、公的調達で評価されるなど地域企業への波及力もある。
- 地域企業へのえるぼし認定取得促進や、育児・介護と仕事の両立支援を進めるとともに、男性の家庭参画支援策を展開していく。
- 若者世代の市内定着とセットで、「働きやすさ」と「暮らしやすさ」の両立を目指す地域政策を強化していく。
- 現時点で若い女性(若者)の流出は改善していないが、内閣官房が公募した「『若者・女性に選ばれる地方』に向け、地域の働き方・職場改革等に取り組む自治体」に参加し、市内外の若者や女性に選ばれるよう働き方や職場の改革を行う市内企業を増やすため、その意識改革、行動変容及び成功モデルの水平展開を促す取組を実施し、今後も「日本一女性が働きやすいまちを目指す!」とのことであった。
所感と本市への反映
酒田市の取組は、単に制度を整備するだけでなく、個々の女性のライフステージや希望に寄り添った支援体制を構築している点において、非常に先進的であった。本市においても、働き方や子育ての多様化に対応した制度設計と同時に、地域全体の意識変容を促す仕組(対話・啓発・協働)をあわせて推進していくことが求められると感じた。中でも、家庭の家事シェア状況を、家族・パートナーと一緒にスマートフォンでチェックできる「家事シェアチェック宣言」や家事代行お試しクーポン等は本市でも推進していきたい事業である。
「義務教育学校(小中一貫校)」について【山形県新庄市】
取組の背景、目的について
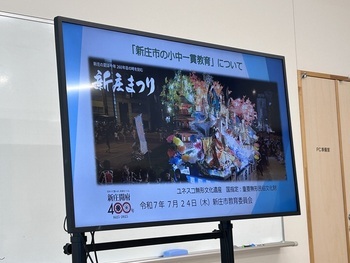
新庄市では、人口減少や少子化、社会の急激な進展、社会構造の変化等に対応した学校再編の一環として小中一貫教育の在り方について検討を進めてきた。その結果、学校教育の様々な課題を解決するためには、学力向上、生徒指導の充実、「ふるさと学習」の充実、小・中学校教職員の協働の視点から、小・中学校がより密接で連続した教育環境をつくることが大事と捉え、小中連携を更に進化させた小中一貫教育を導入することが適切であるとの結論に至った。
2021(令和3)年4月に開校した義務教育学校「明倫学園(小中一貫校)」は、全9学年を通じて、児童生徒がなだらかに進級しながら、「いのちの尊厳を根底に据えた心の教育の充実」を始め、学力向上・ふるさと学習の充実、特別支援教育の充実と4つに重点を置き、小・中学校間で「目指す子ども像」を共有し、系統的な教育体制を目指している。
現在の取組内容について
教員体制については、校長1人・教頭3人を中心に、主幹教諭や専科教員等で編成されており、教科担任制は小学校高学年から導入している。市内には単線連携型、複線連携型の小中一貫もあるが、明倫学園は施設一体型である。
教育システムとしては、4-3-2ブロック(3ブロック制)による教育区分がされている。1年生から4年生までを前期、5年生から中学1年生に該当する7年生までを中期、中学2、3年生に該当する8、9年生を後期としている。
3ブロック制であるのは、学校教育法で義務教育6-3制が定められた1947(昭和22)年当時より、現在の発達が2年早い現状に、今の時代に合わせていく必要があるとの判断からである。
特徴として、
- ブロックごとに最高学年となる4年生、7年生、9年生でリーダーを3回経験できる。
- 異年齢の交流で豊かな人間性と社会性を育むことができる。
- 前・中期段階から一部教科担任制の導入により、専門的な授業を受けることができる。
また、教職員としても、小中の垣根をなくし、義務教育学校の教員として9年間を見通した教育活動を展開できること等が挙げられる。
保護者からは、一貫教育による「学年の壁のなさ」や「教員の連携強化」について、好意的な評価が多く寄せられている。
現在の課題等について
いじめや不登校の発生件数については、近年の取組により減少傾向にあるものの、毎年の定期調査を通じて、子どもたちの心理的安全性の確認を行っている。特に異学年間の交流や担任制の工夫が、自己肯定感の向上、子どもに思いやりの心が育ち、安心感につながっているとされる。また、生徒指導上の問題行動の減少や学力の向上にもつながっている。
一方で、中期ブロックの位置付け等の具体的な検討は必要で、人的資源の適正配置と働きやすい職場環境づくりが求められている。また、中学生該当年齢の生徒の影響により、小学生の問題の早期化も挙げられた。
今後の取組について
児童生徒に対しては、学力向上に向けた授業改善及び家庭学習指導や各ブロックのリーダー育成の強化を行っていくとのこと。
教職員に対しては、教員のマンパワーではなく、「組織」としてのパワーを作り上げていく(多忙化の解消)ことや、各ブロックの目的を意識した、教職員の共通理解を図っていくことが挙げられた。
所感と本市への反映
明倫学園の取組は、義務教育9年間を連続した教育課程として捉え、「学びのつながり」「人間関係の継続」「教員の協働」を基盤に据えていた。異学年交流や教科担任制の導入、保護者との情報共有体制も工夫されており、小中一貫教育の具体的運用モデルとして学ぶ点が多かった。また、授業を見学させていただいたが、9年生と1年生の関わりが微笑ましく、高学年は優しい眼差し、低学年は憧れの心を双方に抱いていることを見て取れた。まさに「あったかい」学校づくりを体現されていた。また、一般的に小学校から中学校への進学のタイミングで増加すると言われる、「いじめ、不登校」の大幅な減少が見られ、「中1ギャップ」が見られないということは特筆すべきことである。
本市においても、小中接続を視野に入れたカリキュラム設計や、教員配置・保護者協働体制の強化を図ることで、子どもの成長を一貫して支える教育環境の実現に資するのではないかと感じた。
「こどもの権利について」(「いじめの防止等に関する条例」を含む)について【宮城県仙台市】
取組の背景、目的について
仙台市では、2019(平成31)年3月に「仙台市いじめの防止等に関する条例」を制定、同年4月から施行した。背景には、中学生のいじめ・自死事案が続いたことなどの社会課題があり、こども・若者の声を行政や教育現場に反映することが求められていた。
「こどもの権利」については、2023(令和5)年4月に「こども基本法」が施行され、2024(令和6)年には「こども・若者の意見の政策反映に向けたガイドライン」が策定されたため、「せんだいこども若者プラン2025」策定に係る意見聴取として、子ども対象のアンケートを10歳から17歳までの8,000人と、18歳から39歳までの6,000人を対象に初めて実施した。また、10歳未満の児童は児童館でのヒアリング等を行った。
現在の取組の内容について
- いじめ防止条例:2019(平成31)年施行の「いじめの防止等に関する条例」の内容ポイントとして、
(1)自分も他人も大切にする子どもを育てる
(2)いじめを誘発するおそれがある「おとな」の行為に注意を促す
(3)地域ぐるみで子どもたちを見守り、育む
(4)いじめを行った子どもの心にも寄り添い、再発防止策を探る
(5)いじめ防止等対策を定期的に検証し、改善を図るとあり、市のいじめ防止等対策の実施状況は、市議会にも報告される。 - 関係機関との円滑な連携やいじめに関する相談機能の強化を図るため、2018(平成30)年度に、市長部局である子供未来局「いじめ対策推進室」、2023(令和5)年度には「いじめ対策推進課」が新設された。
- 学校や教育委員会には相談しにくい、あるいは相談しても解決に至らないという方や、法律や福祉等の観点から対応が必要な方などの相談に対応するため、法律や心理の専門家を中心としたいじめ等の相談窓口「仙台市いじめ等相談支援室S-KET(エスケット)」を2020(令和2)年に開設した。専門員として、特別非常勤・弁護士2人、心理士1人」が配置されている。年間400件程度対応している。
- 広報・啓発として、いじめ防止等対策ポータルサイト「はじめのいっぽ」で啓発動画・著名人や市民からのいじめ防止応援メッセージ等様々な情報を発信し、「社会全体でこどもたちを守る」ということを打ち出している。
「こどもの権利」については、庁内研修を実施し、子どもの権利条約や基本法の知識、傾聴力、質問力、ファシリテーションの向上に力を入れ、全庁的な取組を行った。
現在の課題等について
市民意識調査の結果では、いじめの取組等に関する市民からの評価が相対的に低く、他のアンケートでは、評価すると答えた小学生保護者の割合に対し、就学前児童の保護者は15%程度低い結果となっている。評価に開きがあり、市民全体のいじめの定義や取組などの理解が十分とはいえない状況であるとのこと。しかし、いじめの解消率は80%近くとなっており、認知件数は小さいものも挙げているとのことだった。
「こどもの権利」については、「こどもの権利」や子ども・若者の意見聴取の重要性が社会全体に浸透することが重要であり、周知啓発、学ぶ機会の充実が挙げられた。また、子ども・若者から意見を聴取するためのプラットフォーム開発等の費用負担も課題とのことだった。
今後の取組について
引き続き、現在実施している広報・啓発を継続するとともに、市民全体のいじめ防止に関する認知や理解の向上を図るため、話題性・露出度の高いPRを行っていくとのこと。
「こどもの権利」については、仙台市では、2023(令和5)年11月20日(世界こどもの日)に、外郭団体として、公益財団法人「仙台こども財団」が設立された。今後も、子育て支援団体や地域、企業等とのネットワークを構築・活用し、地域社会全体で子ども・子育てを支える機運を醸成していくための中間支援組織としての役割を担うことで、まち全体が子ども・若者・子育て家庭に温かく、全ての子どもたちが健やかに育つ社会を目指している。
所感と本市への反映
仙台市では、「こどもの権利」を理念として掲げるだけでなく、いじめの防止等に関する条例の整備やこどもプランへの参画制度など、実効性のある取組が進められていた。特に、第三者相談機関の整備や学校・家庭・地域とのネットワークによる協働体制は、子どもを取り巻く環境整備として参考になった。
本市においても、「こどもの権利」について、市民に広く周知・啓発するとともに、子ども・若者の声を尊重し、施策の検討・実行に反映する構造を構築することが重要である。仙台市のように、条例、実践、評価を連動させた一体的な取組が、今後の方向性として非常に示唆に富むものであった。
このページに関するお問い合わせ
議会事務局 議事課
電話:0562-45-6251
ファクス:0562-47-5030
議会事務局 議事課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
