親和クラブ会派行政調査報告 2025(令和7)年1月28日から30日まで
2025(令和7)年1月28日から30日にかけて、長崎県長崎市、佐賀県及び山口県光市を視察しました。
プロスポーツチームと連携したスポーツ振興及び長崎スタジアムシティプロジェクトとの連携体制について【長崎県長崎市】
取組の背景及び目的
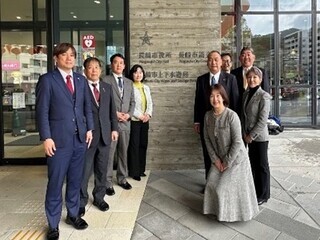
2015年7月、三菱重工が「2018年3月に幸町工場機能廃止」を発表し、「スマートサスティナブルなまちづくりを先導する拠点」をコンセプトに跡地活用事業者を公募した。2018年4月に株式会社ジャパネットホールディングスが優先交渉権者に決定し、基本協定書が締結された。そして、ジャパネットグループがサッカースタジアムを中心にアリーナ・ホテル・オフィス・商業施設を併設し、様々なワクワクが詰まったまちづくりを進める「長崎スタジアムシティプロジェクト」に取りかかることとなった。
2018年4月頃から、ジャパネットが、市等の行政に対して「まちづくり」に対する相談等をするようになり、長崎県と長崎市は、協議会や検討推進チームを組成して、ジャパネットの「長崎スタジアムシティプロジェクト」をサポートする体制を構築していった。
取組の内容と現在の状況
- 民間が事業主体の中心となって動き出したプロジェクトに対し、市の支援としては、用途地域の変更(工業地域→商業地域)、国の優良建物等整備事業制度を活用した補助、鉄道高架下横断箇所及び歩道の整備、「Vロード」と称した長崎駅及び浦上駅と長崎スタジアムシティ間の歩行者動線を案内誘導板、デザインマンホール、バナーフラッグ、のぼり旗、路面投影機等の設置整備、企業版ふるさと納税の活用等を行った。
- 長崎スタジアムシティ開業により、プロスポーツチームの地域定着や、「市民の楽しみ」、「まちの賑わい」、「こどもの学び」など、開業効果が地域経済やスポーツ等あらゆる分野へ波及することを目指し、開業前から「まち全体」で長崎スタジアムシティの開業機運の醸成を図るために、路面電車、路線バスにPR用のラッピングをして市内を巡回したり、商店街等にフラッグ・バナー・のぼり等を設置したり、SNS等の動画配信による情報発信を行っている。
- 長崎市をホームタウンとするプロスポーツチームであるV・ファーレン長崎及び長崎ヴェルカの両チームの「見るスポーツ」を通じて、スポーツへの関心と地元の応援機運を高めていくために、ホームゲームでは、市内在住の小・中学生親子ペアを無料招待する市民応援DAYを実施している。また、アウェイゲームではパブリックビューイングを長崎駅広場や市役所庁舎1階ロビーにて実施予定している。
所感
民間の大きな資本が投入されたことによって実現できたプロジェクトだが、その動きに乗じて市として「推進委員会(副市長を委員長とし、11の部局で構成されている)」を設置し、この事業への支援を行っている。スピード感を持って事業を推進するに当たり、縦割りでそれぞれが対応するのではなく、部局の連携が欠かせないと感じた。
本市においても、新しい事業に携わる際には上記の良さをふんだんに取り入れ、部局を超えて、横断的に連携し、職員がやりがいを感じられる事業展開を進めていくことが重要と考える。
長崎スタジアムシティスタジアムツアーについて【長崎県長崎市】
取組内容

長崎スタジアムシティツアーは、普段は立ち入ることができないピッチやバックヤード、選手ロッカーなどを見学できるツアーで、専門ガイドによる案内のもと、スタジアムやアリーナの魅力をより深く体感することができる。
長崎スタジアムシティは、サッカースタジアムを中心として、アリーナ、ホテル、オフィスビル、商業施設を配置している。
サッカースタジアムには、ホテルが隣接し、ホテルからも試合観戦ができる。また、サッカー専用スタジアムをコンセプトに設計されているため、観客席とグラウンドとの距離がかなり近く、グラウンドと同じ高さで、かつ、フェンスもない座席もあり、試合観戦における臨場感は、他のスタジアムと比較にならないほど味わえるつくりとなっていた。また、商業施設や飲食店等にも力を入れており、そして、オフィスビルから商業施設までジップライナーが楽しめる機能もあり、試合がなくても楽しめる場所として創意工夫されている。
所感
スタジアムツアーを利用する選手に対しては、敵・味方関係なく細部にまで配慮が行き届き、親切で便利な施設になっており、その公平で優しい配慮が観客にも伝わり、もっと応援したくなるという好循環をもたらしていると感じた。
今回の視察では、細部にまで行き届いた配慮が施されていれば、利用者が増え、運営側の収益も増え、市の税収も人口も増えるといった期待が持てると感じた。
本市において、今ある体育施設の老朽化などの整備をする際も、スポーツ施設としての形をなしていれば良いということではなく、利用者の今後の成長や発展を見据えた長期的な計画をもって整備することにより、市の発展に繋げていけると考える。また、付加価値のある魅力的な要素を取り入れ、市内外にその魅力を発信すれば、施設やイベントを目指して観光客や参加者を呼び込むこともでき、市内の商業活動が活発になり、経済効果も期待できる。是非そのような視点でスポーツ施設の整備を考えていく必要があると考える。
さがデザインについて 【佐賀県】
取組の背景及び目的

「さがデザイン」とは、行政(佐賀県)が実施する事業をデザインの視点で計画・展開し、新たな価値を付与することで、「人のくらし、まち・地域を心地よくし、豊かなものにする」という取組である。現在3期目の山口知事は元来デザインに対する思い入れがあり、就任当初(2015年)からこの取組が始まった。設立当時は2名で始まった組織である。
取組の内容と現在の状況
行政は、元々法律で決められたことを、正しく執行する役割を負っている。そのため、何か決まりがあることに対して、正しい答えを出すことは得意である。しかし、最近言われている地域づくりや地方創生には正解がない。正解がないことに対して答えを出していくということを、職員は訓練されていない。そういう組織でクリエイティブなアイデアを通そうとすると、とても時間が掛かり、アイデアも丸められてしまう。そこで、このピラミッドの外に意思決定の機能を置き、尖ったアイデアをそのまま出そうという試みが「さがデザイン」である。
行政組織では、まず内部で職員が企画を立案し、必要に応じ外部の利害関係者のヒアリングを行って事業を形にしている。しかし、そのプロセスには、「そもそも」のコンセプトから物ごとを紐解いて考えるデザインの視点が足りない。「さがデザイン」の活動は、こうした行政の事業のコンセプトに、広義のデザイン視点を加えることでもある。
そのときに協業するのが、「さがデザイン」の強力な外部パートナーである、デザイナーなどクリエイターやコンサルタントを始めとする専門家のネットワークである。「さがデザイン」の立ち上げに当たり、佐賀出身のクリエイターを中心に、約半年間、ひらすら人に会って回り、「佐賀のプロジェクトに協力してほしい」と話をしてネットワークを構築していった。その数は現在では約100人にのぼる。こうした専門家たちが「さがデザイン」を通じて事業立案のアドバイザーになったり、さらには、事業の実施プロジェクトチームの一員として協力している。
- 「交通事故ゼロ」を目指して2018年にスタートした「SAGA BLUE PROJECT」 集中力を高めると言われる青色を基調として、交差点の中を青色の四角枠で舗装し、ドライバーに交差点の存在を視覚的に訴えてスピードの出し過ぎや急な進路変更を抑制する効果を狙った。テレビCMや県民参加型のイベントも実施し、県民一人一人が自身の行動を変えていくことを目指している。県の人口10万人当たりの人身交通事故発生件数は、2018年には699.0件(ワースト2位)だったが、2022年になると401.7件(ワースト3位)と減少し、効果はじわりと見えてきている。
- 「さがアグリヒーローズ」 農業の6次産業化をキーワードに若手農家がクリエイターと連携して収益増を目指す事業で、5組の農家・グループが参加して2019年にスタートした。それぞれにクリエイティブチームが編成され、商品開発やロゴマークやウェブサイト作成などを支援した。5組とも「4年間で販売額1000万円増」の目標を3年目までに達成しており、2023年度から第2期が始まっている。
所感
全ての行政事業・施策には課題解決に向かっての目的があり、事業をデザインしていく過程で、行政が目指す「まちの形」「コンセプト」に沿っているか、事業の目的は何か、どのような効果を期待するのか(効果を上げるにはどうすればいいか)、どのように進めるか等々を担当部局以外の視点で確認し、わかりやすい表現に加工して進めていくという取組は大変興味深いと感じた。
また、この取組には新しいアイデア、遊び心などが多く取り入れられており、住民の興味関心を呼び込む効果も期待できる。このことにより、わが町自慢、シビックプライドの醸成にも大いに役立つことと思われる。
行政職員や住民のアイデアを積極的に取り入れていくことが、職員のモチベーション向上や住民の政治参加促進につながるということは、これまでも至る所で語られてはいるが、現実的にそのようになるか否かは首長の度量によるところが大きい。そういった点で、本市の環境はどうなのか、佐賀県のこの取組事例は参考にしたいところである。
以上のように、さがデザインの取組は様々な効果を期待できるものであり、こうした取組は大府市においても一考の余地は十分にあると感じた。
コミュニティ・スクール及び小中一貫教育について【山口県光市】
取組の背景及び目的

コミュニティ・スクールに関する議員からの質問を契機として検討が始まり、2009年に文科省指定校として浅江中学校にてコミュニティ・スクールの導入が始まった。その後、中学校から順次導入を進め、2012年には全ての小中学校(16校)でコミュニティ・スクール推進事業を開始した。2020年には、コミュニティ・スクールを基盤とした小中一貫教育を導入し、これからの社会を生き抜く子どもたちに求められる資質・能力を確実に身に付けるため、小・中学校が「同一の共通で目指す15歳の子ども像」を共有し、「9年間の系統性を整理した教育計画」に沿って、積み重ねや連続性を考慮した教育活動を推進している。
取組の内容と現在の状況
- 教職員の負担を軽減させつつ実践的なプロジェクトとするために、教職員が意見や企画を取り入れる形ではなく、自ら提案してもらう環境にしている。また、コミュニティ・スクールの活動を校務分掌の仕事にし、負担に感じさせない工夫を行っている。
- 小中一貫教育の推進体制としては、前期(1~4年)、中期(5~7年)、後期(8~9年)に分け、9年間の系統性・連続性に配慮した学習指導・生徒指導を行っている。校舎の場所は同じではなく、意識としての一貫教育であり、方向性は揃えている。
- コミュニティ・スクールは、学校運営協議会を設置した学校であり、学校運営協議会は、保護者や地域住民等の意見を学校運営に反映させるための協議や基本方針の承認などを行い、「特色ある学校づくり」を図る仕組みである。光市では、中学校区で「15歳の子ども像」を共有し、学校、家庭、地域がそれぞれ子どもと真剣に向き合い、子どものことを真剣に考える「共に育てる+共に育つ」の視点のもと、お互いに自らできることについて、知恵を出し合う活動を通して、学び合う組織と学びでつながるコミュニティ・スクールを目指し、令和6年度の重点取組事項を以下の3点とした。
- 学校や子どもたちを取り巻く課題を共有し、熟議を通して課題解決に向けた学校支援や協働生活について協議する。必要に応じて、子どもたちの熟議への参加等を積極的に進める。
- これからの社会の創り手となる子どもたちに、社会や地域と向き合い、関わり合いながら学ぶ機会を与える「学校・地域連携カリキュラム」の改善サイクルを構築する。
- コミュニティ・スクールが、学校はもちろん地域にとっても意義あるものにしていくために、地域にわかりやすい説明を行うなどの情報発信を工夫する。また、学校に関わる地域人材を発掘する。
課題
- 人によって、学校への関わり度合いの差が大きい。
- 地域の方が関わっているから関わらなくてもよいと、保護者に当事者意識がなくなってしまう。
- いつも同じメンバーとなり、世代交代ができない。
所感
地域における諸課題については、大府市も同様の問題を抱えており、家庭の変化や人間関係の希薄化による地域における教育力の低下、教員不足や教員の働き方改革の必要性による教育環境の変化を踏まえると、地域の人材や物的資源を活用しながら学校と地域社会が一体となって子どもたちを育成する体制は、持続可能な質の高い教育の保障において必要不可欠な取組であると言える。さらに、義務教育を小中一貫教育とすることで、9年間を掛けて子どもたちを育成するという考え方は、近年の「中1ギャップ」という問題の解決につながり、将来的には不登校(長期欠席)児童生徒の増加という現状についても、一定の歯止めを掛けることができると考える。
日頃から、児童生徒たちが、学校の中で地域の大人たちと関わることで、学校とは関係なく地域とのつながりを深めることができ、地域の行事等にも積極的に参加しようという気持ちが醸成され、それが郷土愛を育み、最終的には自分たちの生まれ育った土地に住み続ける選択をするという良い循環が生まれるのだと実感した。
本市においては、既に見守り活動等、地域住民が学校と連携した取組を行っている事例もあるので、今の時点でコミュニティ・スクールが新たな取組と捉えると負担感を感じて尻込みをしてしまうかもしれないし、負担感については教職員に対しても同様で、やらされ感を持たせないために、コミュニティ・スクールのための意見や企画を教職員に提案してもらう環境を整える必要があると感じた。
また、現在は自治会や子ども会等、地域組織への加入者の減少や役員の成り手不足が全国的な課題となっている中で、コミュニティ・スクールの役員の確保も非常に難くなると考えるので、今のうちから意義をしっかりと理解してもらうよう丁寧な説明が必要と考える。
今後、本市で導入を検討する際、組織的な学校運営協議会制度の運用については、課題があると考える。学校と家庭、学校と地域の連携や協働の重要性を考えると、光市のように教育委員会内に学校教育課と文化・社会教育課が設置されている組織であれば、横断的な連携を図ることも容易に可能であるが、本市教育委員会内には学校教育課のみで、社会教育に当たる部署は協働推進課内に設置されている。現状では部署を超えての連携はかなり難しいと考えるので、職員は、「さがデザイン」の取組を意識して行政運営を進めていくことが必要である。
このページに関するお問い合わせ
議会事務局 議事課
電話:0562-45-6251
ファクス:0562-47-5030
議会事務局 議事課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
