親和クラブ会派行政調査報告 2025(令和7)年7月2日から4日まで
2025(令和7)年7月2日から4日にかけて、北海道札幌市、室蘭市及び士別市を視察しました。
札幌市子ども発達支援総合センター「ちくたく」の取組について【北海道札幌市】
取組の背景・目的
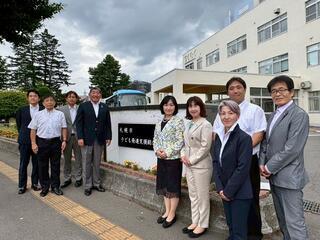
1934(昭和9)年、成人を対象とした市立病院の精神科分院として開設された市立札幌病院静療院であったが、1973(昭和48)年に小児特殊病棟が開設され、1982(昭和57)年には第一種自閉症児童施設のぞみ学園が開設された。
2009(平成21)年から保健・福祉・教育が一体となって子どもの心の健康増進を図るため、一般行政病院化に向けた検討を行い、2012(平成24)年に成人部門を市立札幌病院に移し、札幌市児童心療センターを開設した。
2015(平成27)年、子どもの心身の問題に対して早期支援を実施するために、部門ごとに分散していた機能と施設を一カ所に集約して、札幌市子ども発達支援総合センター「ちくたく」を開設し、包括的かつ継続的な支援体制を構築した。
取組の内容
「ちくたく」は、子ども心身医療センターと発達医療センターの医療部門、児童心理治療センター「ここらぽ」と自閉症児支援センター「さぽこ」の入所施設部門、かしわ学園(福祉型児童発達支援センター)、ひまわり整肢園(医療型児童発達支援センター)、はるにれ学園(福祉型児童発達支援センター)、みかほ整肢園(医療型児童発達支援センター)の通所施設部門、地域支援室の総合相談部門で構成されており、「多様な視点による適切かつ高度な支援の提供」と「関係機関との連携による札幌市全体の支援体制の向上」をコンセプトに、医療と福祉の総合施設として運用されている。
子ども心身医療センターの診療科は児童精神科、小児科、整形外科、耳鼻咽喉科、眼科。心身の発達に遅れ・障がいが疑われる子どもや、心に悩みを抱える子どもを医学的に診断し、心理治療や精神科デイケア、リハビリテーション、家族支援、各種相談等を実施している。自閉症スペクトラム障がいが多い。原則18歳未満の子どもが対象で、児童精神科の初診は中学生までとなっている。診察は予約制で、1年間を4カ月ごと、3期に分けて電話予約としているが、受付開始後は1日で予約枠がほぼ満席になってしまう。他の民間施設も同様に数カ月待ちで、児童精神科医が不足している状態である。
児童心理治療センター「ここらぽ」は、主に心理治療を必要とする子どものための児童福祉施設である。心の悩み等が要因で地域や家庭での生活が困難な子どもを、児童相談所の措置により一定期間預かり、生活面や心理面での支援を実施している。対象は原則18歳未満で、入所・通所の判断は児童相談所による。定員は入所23人、通所5人である。札幌市立平岸高台小学校・中学校のぞみ分校に通学しており、特別支援学級扱いとなっている。
自閉症児支援センター「さぽこ」は、児童福祉法による障害児入所支援と障害者総合支援法による短期入所(ショートステイ)を行っている。個別的な支援計画に基づく日常生活スキルに関する支援を提供し、通所・入所にかかわらず、子どもたちの状態改善を図る取組を実施している。対象年齢は原則0歳から18歳になる誕生日まで。対象障がいは自閉症を主とする障がい児。措置入所、契約入所のどちらもあるが、現在は措置入所が多い傾向である。定員は入所27人、短期入所5人である。義務教育として、のぞみ分校に通学している。
地域支援室は相談業務全般を担っており、ちくたく内の調整業務や児童相談所、教育センター等との情報連携、地域支援、他機関連携を行っている。
所感・大府市への反映
- 医療と福祉の複合施設として様々な機能が1カ所に集約されていることで、常時行き来をして連携が図られ、関係者間での情報共有が迅速かつ的確に行われているため、個々の子どもの特性に配慮した、きめ細かな支援が可能となっている。また、いろいろな立場の意見を聞くことで視野を広げることができており、すばらしいと思った。
- 入所施設の現地視察では、スタッフの方からお話を伺ったが、本市には入所施設がないため、初めて現場の生の声を聞き、入所している子どもたちを目の当たりにして、少なからず衝撃を受けた。保護者による虐待や養育拒否等、児童相談所の判断によって入所する措置入所と、保護者と施設が契約を交わす契約入所の2種類があるが、ほとんどが措置入所とのことで、辛い立場にある子どもたちを、日々、懸命にサポートしている職員の方々には頭が下がる思いだった。
- 本市にも発達支援センターおひさま、みのり等の施設があり、適切に支援していると思うが、発達が気になる子への支援は早期発見・早期療育が大切だと考える。これまで、本市の親子育成支援事業(ジョイジョイ)は2歳児からの親子を対象としていたが、今後は1歳6カ月児健診をきっかけに支援を受けられるようになるので、大いに期待している。
- 本市においても「医療」と「福祉」を1カ所(同一施設内)で連携できるシステムができるとよい。しかし、本市には市民病院がないため、(1)あいち小児保健医療総合センターとの連携、(2)近隣病院との連携による医師の派遣などができるとよい。
- 保健センターで乳幼児健診(1歳6カ月児健診、3歳児健診など)を実施した際、発達等の心配や相談があった場合は、診療やカウンセリングの予約までできるとよい。
- こども若者支援課と教育委員会との強い連携が必要である。
- 本市は、半田市にある児童相談所(知多児童・障害者相談センター)の管轄下にあるため、福祉機能としての入所施設に関しては、本市独自の取組を実施することが非常に難しい状況にある。一方で、医療機能としての取組については、大いに参考となるものと捉えている。
- 心身の発達に特性を持つ子どもへの支援においては、早期発見と早期治療の開始が何よりも重要である。早い段階で診断を受け、適切な治療や訓練を始めることにより、個人差はあるものの、発達の改善が大いに期待でき、さらには子ども本人の社会的自立に向けた支援にもつながると考える。
- 本市においては、発達に特性を持つ就学前の子どもに関しては、市公式ホームページ上で「発達支援センターおひさま」が相談や支援の窓口として案内されている。しかし、就学後の子どもに関しては明確な案内がなく、「大府市ふれ愛サポートセンター」で高齢者、障がいのある方、また長期欠席の児童・生徒の相談・支援を担っている状況であるため、支援を必要としている親子が切れ目のない支援を受けられるよう、相談窓口はワンストップで完結するような環境整備が必要と考える。
町内会活性化の取組について【北海道室蘭市】
取組の背景
室蘭市の町内会加入率は、1988(昭和63)年の94.5%をピークに一貫して減少傾向にあり、2024(令和6)年には57.2%にまで低下した。特に、若年層や集合住宅居住者において未加入の傾向が顕著であり、地域コミュニティとの接点が希薄化している。加えて、構成員の高齢化が進行し、役員の担い手確保が困難となっており、一部の会員に業務負担が集中することで、組織運営の継続性が懸念される状況にあった。
取組の内容
町内会加入率の低下や担い手不足等の課題を受け、2021(令和3)年12月に「室蘭市町内会・自治会活性化推進会議」を設置した。2023(令和5)年3月に町内会の目指す姿の実現に向けて、4つの基本方針と11項目の取組の方向性、27項目の具体的な取組で構成された「室蘭市町内会・自治会活性化基本方針」を策定し、段階的に施策を展開している。
基本方針
- 参加しやすい環境づくり
- 活動を支える担い手の確保・育成
- 地域課題に対応した活動の充実
- 将来を見据えた持続可能な組織づくり
注目すべき主な取組
- デジタル化の取組
2022(令和4)年度から2023(令和5)年度に、情報伝達の迅速化、役員の負担軽減、若年層の参加促進を目的にデジタル化推進モデル事業を実施し、現在は市民団体と連携して、希望する町内会に対してデジタル回覧板(LINE公式アカウント)の導入を進めている。コロナ禍で「非接触」を推奨する中で浸透し、2024(令和6)年度までに7団体へ普及している。紙回覧板とデジタル回覧板のそれぞれの長所・短所を認識しつつ、併用をしている町内会が多い。 - 学生向け出前講座の開催
町内会活動に対する学生の理解を深め、町内会役員との交流・意見交換を行う場として出前講座を開催している。 - チラシによる参加啓発
小中学校・保育所・幼稚園等の保護者や、市内の企業等の退職者に向けた啓発チラシにより、町内会への加入や担い手確保の取組を促進している。最近はQRコードによる申込みが増加傾向にある。 - 町内会サポーター制度
町内会が主催するイベントの運営に協力可能な市民や企業・団体を「町内会サポーター」として登録し、町内会の依頼に応じて派遣している。現在、約70人が登録している。 - 市民活動団体と町内会との連携事業
市民活動団体と町内会が連携して地域課題の解決や町内会活動の充実を図るため、まちづくりのスキル・ノウハウ・アイデアを持つ市民活動団体から町内会と連携して実施できる企画を募集し、市は、提案のあった企画を町内会に紹介し、活用を希望する町内会とマッチングしている。対象団体は室蘭市市民活動センターの登録団体で、対象となる企画は、町内会の役員・会員等を対象としたイベントや研修等の実施、専門知識やノウハウの提供等である。 - 町内会活性化推進条例(仮称)の制定
2025(令和7)年度末までに、町内会の役割や重要性を市民が共有し、町内会活動を地域住民、事業者、行政が一体となって支えていくことなどを目的とした理念条例を策定し、2026(令和8)年4月の施行を予定している。
所感・大府市への反映
- 室蘭市は、かつて人口16万人を超える中核都市として発展を遂げ、20万人都市を目指したまちづくりを推進してきたが、構造不況やグローバル競争の激化により、基幹産業である製鉄・造船業が縮小し、加えて若年層の流出や少子化が進行し、現在では人口約7万人にまで減少している。こうした人口構造の劇的な変化は、地域コミュニティの在り方にも影響を及ぼし、町内会・自治会を145団体維持し続けることが困難になっている現状がうかがえた。
一方、本市は現在もゆるやかな人口増加傾向にあるが、その基盤は自動車産業への依存が大きく、今後、産業構造の変化によっては人口維持が困難となる可能性も否定できない。将来を見据えた産業多様化の視点からも、ウェルネスバレー地区を中心とした先進企業の誘致と新産業の育成が重要であると改めて認識した。 - 人口が長期にわたって減少していく中で、町内会役員の高齢化、加入率の低下に対しての対策に苦慮しているのは、本市でも同様である。本市との違いは、7万人程度の人口に対して145もの町内会が存在していることであり、このことも町内会衰退の一つの要因ではないかと推察する。それぞれの町内会には地縁、歴史など様々な事情があると察するものの、町内会活動の負担軽減や効率化をにらみ、本市でも自治区、自治会の再編は将来に向けて念頭にしておくべきと感じた。
- LINEを活用したデジタル回覧板については、今や高齢者の多くがLINEを日常的に活用していることから、情報提供ツールとしては有効であろうと思う。回覧板のような日常的な情報ツールからデジタル化を図ることは、高齢者へのデジタル活用の抵抗感を軽減させる効果も期待できるのではないか。
- 本市においても、ICTを活用した地域情報共有の仕組みづくりは、今後の町内会・自治区の運営において有効であると感じた。
- 町内会活性化基本条例(仮称)の制定について、その一番の目的が「市の責務」を明記するとのことであった。本市でも、「町内会は住民の自主運営」を盾に、町内会運営に関して積極的な関与を回避する姿勢が見られる中で、一定程度の行政の責務を明記することは意義があると考えた。
- 町内会サポーター制度については、現在、地域のイベントにおける補助を目的としており、原則、無償、有償については、町内会に任せているとのことである。今後、町内会サポーターの登録者を増やしていくためには、有償にするのが効果的ではないか。また、イベント時だけでなく、通常業務の担い手不足の解消へとつなげていくこともできるのではと考える。
本市にも、こうしたサポーター制度を取り入れることで、課題となっている自治会離れの要因の一つの解消に繋がるのではと考える。
生涯学習センター「きらん」について【北海道室蘭市】
取組の背景

室蘭市では、人口が最盛期を迎えた1955(昭和30)年から1965(昭和40)年代に整備された公共施設が多く、平成初期には老朽化やバリアフリー未対応といった課題が顕在化していた。しかし、基幹産業の構造不況や人口減少に伴う財政の悪化から、長らく抜本的な対応が困難な状況にあった。
そうした中、耐震診断により多くの施設で耐震性能の不足が判明し、公共施設の在り方が庁内共通の課題として、政策推進本部会議で協議されるようになった。個別施設ごとの対応方針を検討する中で、複数の機能を集約する「複合公共施設」の整備方針が策定され、現在、事業が進められている。
また、室蘭市では小中学校の統廃合も進めており、本事業用地は廃校となった中学校跡地で、交通利便性にも優れる商業地域中心部に位置することから、集約施設の建設地として選定された。
取組の内容
生涯学習センター「きらん」は、人口減少により統廃合される学校施設などの跡地利用として、市内各所に点在していた総合福祉センター、青少年研修センター、中島会館(社会・文化活動拠点)及び市民活動センターを集約し、図書室、子育て支援施設(キッズパーク・プレイコート)、市民活動支援スペース、工芸・料理・音楽などのスタジオや会議室、カフェを備えた交流広場など、多世代交流と学びを促進するための機能を兼ね備えた複合公共施設である。福祉相談窓口としての機能はなく、全世代を対象とした「居場所」としての機能を有する。
事業費の抑制、サービスの向上、管理運営経費の抑制、余剰地の有効活用という課題への対応策として、民間活力導入手法の一つである「DBO方式」を採用し、付帯事業として「24時間営業のゲート式有料駐車場」「ビジネスホテル事業」も行っている。
集約施設に継承すべき既存施設の機能、集約施設に新たに導入すべき機能及び多世代の交流拠点として必要な機能を把握するため、市民ワークショップや小規模意見交換会など、新たな市民意見集約手法を取り入れている。
所感・大府市への反映
- 施設を一巡して、まず感じたことは、「ここで一日中過ごせる」ということだ。そして、利用に関しても、本市の公民館利用と異なり、団体登録をすることなく、個人でも利用が可能であり、営利目的でも利用することができるとのことであった。室蘭市には「公民館」というものが存在しないという背景もあるのだろうが、多様な市民の嗜好に対応するためには、利用者の制約は限りなく排除すべきだと感じた。
- 子ども向けの遊戯施設は、スペースが十分に確保され、子どもたちのわくわく感を刺激するような工夫が随所に施されていた。計画段階から多くの市民の声を聞きつつ事業を進めてきており、自分の発案で設置された設備や器具があれば、「自分たちの施設」という意識が高くなるものと思われる。
本市の「おもちゃ美術館」を始め、様々な施設の整備に関しても、市民の声を積極的に取り入れ、公開するという姿勢は見習うべき点であろう。 - いつでも誰でも気軽に立ち寄ることができ、一日中過ごすことが可能な空間となっているため、様々な人にとっての居場所となっていると感じた。
本市においても、現在、老朽化対策等が課題となっている社会福祉協議会の拠点を考慮に入れつつ、屋内遊び場や、交流ひろば、市民活動センターを盛り込み、世代や分野を超えた様々な人が集まり、出会う拠点を整備してみてはどうかと考える。 - 生涯学習センター「きらん」は、公民館を持たない室蘭市において、世代や目的を問わず、市民が集える場として、非常に有効に機能していた。特に子どもの遊び場は天井が高く広々としていて、天候に左右されずに安心して遊べる環境が整っており、子育て世代からの支持が厚いと感じた。また、研修室やスタジオは団体登録が不要で、個人利用や営利目的にも対応しており、市民にとって使いやすい柔軟な運用がなされている点も印象的だった。図書館を始めとした施設全体においても、市民の声が随所に反映されており、まさに「市民とともにつくる施設」としての姿勢が伝わってきた。
本市においても、公共施設の利便性を高めるために、利用条件や予約方法の簡素化・柔軟化を進め、市民の声を丁寧にくみ取った施設運営を目指すことが、更なる愛着と利用促進につながると考える。
士別市農業・農村活性化計画について【北海道士別市】
取組の背景・目的

士別市は、豊かな自然環境と水資源を活かした稲作・畑作・畜産を基幹産業として発展してきた。しかしながら、農業者の高齢化や担い手不足、農畜産物価格の低迷などが課題となり、対策が求められていた。
これを受け、2000(平成12)年に農業・農村活性化条例を制定し、地域ぐるみで農業と農村の持続的な発展を図る取組を開始した。
取組の内容
現在は、第4次農業・農村活性化計画」(2022(令和4)~2025(令和7)年度)を推進しており、以下のような施策が展開されている。
• 計画の基本方針:「人づくり」、「農村づくり」、「土づくり」、「収量アップ」の4本柱を設定
• 担い手育成:地域おこし協力隊(農業支援員・酪農・めん羊飼育)を活用し、就農相談会や道内大学等へのPR、就農体験の受入れ等を実施
• 労働力対策:繁忙期における人材派遣やファームコントラクターによる作業委託を推進
• スマート農業:ICT等を導入し、作業の効率化と省力化を支援。国の補助金も活用
• GAP(農業生産工程管理)対応:農作業記録の「見える化」により、信頼性向上と経営改善を図り、講座開催などで理解を促進
• 土づくり支援:たい肥・緑肥の導入に対して中山間地域等直接支払交付金を活用
• 移住促進:市外からの若者参入を促すため、出会いの場の創出や生活支援制度を整備
所感・大府市への反映
- 士別市では、少子高齢化による担い手不足に対して、地域・農協・行政が連携し、実践的な支援体制を構築している点が印象的であった。特に、新規就農者への支援については、国の制度に頼るだけでなく、市の予算も活用して都市部以外の研修生も受け入れており、柔軟な対応が評価される。また、地域に馴染んでもらうために祭りやイベントへの参加を促すなど、地域定着への工夫もなされていた。
一方で、担い手不足により大規模水田を維持できず、畑作化を余儀なくされる事例も見られ、国による早急な支援制度の見直しが必要と感じた。 - 本市においても、JAと行政が一体となって営農支援に取り組む姿勢が求められる。新規就農者の受入れに際しては、住居や生活面の支援制度を整備し、安心して農業を始められる環境づくりが必要である。空き家や市営住宅の無償提供、意欲ある人材と既存農家のマッチング支援などを通じて、持続可能な地域農業の実現を目指すべきである。
- 現状として、「耕作放棄地がない」という状況はすばらしい。
- 農家の状況を徹底的にリサーチすることが重要であると感じた。行政が、同地区内(士別市では4地区に分かれている)の近隣農家のネットワークを活用し、「離農しそうな農家」の情報を素早く入手し、実際に状況を聞くことで「あと何年くらいで離農しそう」というリアルな情報をいち早くつかむ。これにより、新規就農者の研修を早い段階から企画できる。また、離農して担い手がいなくなった農地を周囲の農家に依頼して耕作してもらうことにも役立っている。
- 農業振興課職員が担い手確保にも積極的に動いており、地域の農業学校などに出向いて自治体ベースで就農説明会を開催している。なお、士別市では、就農による移住者向けに家賃助成制度が用意されている。
- 機械化・ICT導入による作業の省力化・効率化を進めることで、より大規模な経営が可能となり、農業を「魅力ある職業」として再定義することができる。これが結果として、本市における食料の安定供給につながるものと考える。
このページに関するお問い合わせ
議会事務局 議事課
電話:0562-45-6251
ファクス:0562-47-5030
議会事務局 議事課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
